こんにちは。
株式会社レティシアン 専属獣医師の金子 潤です。
 ワンちゃんが動物病院を受診する理由のうち、
ワンちゃんが動物病院を受診する理由のうち、
多くの割合を占めるのが「皮膚のトラブル」。
トラブルが発生したら早めに動物病院を受診するのはもちろんですが、
皮膚の健康を守るためには日頃のケアがとても重要です。
今回のコラムでは、知っているようで意外と知らない
「ワンちゃんのシャンプーのしかた」
について解説していきます。

こんにちは。
株式会社レティシアン 専属獣医師の金子 潤です。
 ワンちゃんが動物病院を受診する理由のうち、
ワンちゃんが動物病院を受診する理由のうち、
多くの割合を占めるのが「皮膚のトラブル」。
トラブルが発生したら早めに動物病院を受診するのはもちろんですが、
皮膚の健康を守るためには日頃のケアがとても重要です。
今回のコラムでは、知っているようで意外と知らない
「ワンちゃんのシャンプーのしかた」
について解説していきます。
人間の皮膚(表皮)の厚さは約0.2mmといわれているのに対し、ワンちゃんの表皮はその1/5~1/3程度の厚さしかないといわれています。
皮膚が薄い分、外部からの刺激にデリケートで、それを補うために全身を毛で保護しているとも考えられています。
私たちの身の回りには、ウイルスや細菌・真菌などの微生物、花粉やハウスダストなどのアレルゲン、紫外線など、体に悪影響をおよぼす様々な刺激があふれています。
ワンちゃんの皮膚は、これらの刺激から体を守る鎧のような役割を果たしています。
さらに、生命維持に重要な水分やミネラルなどが体外に流出してしまうのを防ぐ役割も果たしています。
この「外界から体内への侵入」「体内から外界への流出」が起こらないように体を守る機能のことを皮膚の「バリア機能」と呼びます。
皮膚の中には様々な刺激を感じ取るセンサーが備わっていて、「熱い」「冷たい」「痛い」「圧迫されている」「痒い」などの感覚を脳に伝える役割を果たしています。
外界の温度に合わせて、皮膚の血管を拡張・収縮させたり、季節ごとに毛量を調節したり、毛を逆立てたり、皮膚からの分泌物の量を調節したりして、体温の調節を行っています。
 シャンプーだけじゃない、ご自宅で
シャンプーだけじゃない、ご自宅で洋服を着せることによって、皮膚を物理的に保護したり、環境中のアレルゲンが皮膚に付着するのを防ぐことができます。ワンちゃんの毛や皮脂、フケなどが洋服の内側に付着するので、こまめに着替えるようにしましょう。通気性の良い素材のものがおすすめです。
ワンちゃんの寝床や生活スペースをこまめに掃除し、クッションやマットなども定期的に洗濯するようにしましょう。また、皮膚にかかる刺激を少なくするために、柔らかく摩擦の少ない素材のグッズを使用するようにしましょう。
人間と同じように、ワンちゃんの皮膚も紫外線によってストレスを受けてしまいます。
特に白い毛のワンちゃんは紫外線が皮膚まで届きやすいため、注意が必要です。
夏場の紫外線が強い時期は、できるだけ日陰を歩くようにしましょう。
日常的にブラッシングやマッサージを行うことによって、毛に付いた汚れや抜け毛を取り除くことができます。また、毛の流れを整える際に毛先まで皮脂を行き届かせて毛をコーティングする効果や、皮膚に適度な刺激が加わることによって皮膚の血行改善・適度な皮脂分泌を促す効果も期待できます。
霧吹きなどを使って毛を軽く湿らせてからブラッシングを行うと、ブラシの滑りが良くなって毛や皮膚への刺激を軽減でき、抜け毛や汚れの除去効果も上がることが分かっています。
健康な毛や皮膚を維持するためには、栄養バランスの整った食事が欠かせません。
毛や皮膚の主成分となるタンパク質をはじめ、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルの5大栄養素がバランスよくとれる食生活を心がけましょう。
首輪・ハーネス・ヘアゴムなどをつけっぱなしにすると、ワンちゃんの毛や皮膚に負担がかかってしまうことがあります。
ご自宅の中では首輪などを外すようにして、毛や皮膚に継続的な負担がかからないようにしてあげましょう。
日光を浴びることが、ワンちゃんの健康的な発毛サイクルを維持するために重要なことがわかっています。
毎日のお散歩に行くのはもちろん、ご自宅の中に日光が入るようにしてあげることをお勧めします。
外界の温度変化も発毛サイクルに影響することがわかっています。
エアコンなどを活用し、室温が激しく変動しないように調節してあげましょう。
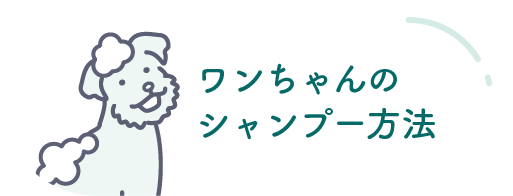 ワンちゃんのシャンプーは、外からの汚れ(ゴミ・土・ホコリなど)と中からの汚れ(抜け毛・皮脂・フケなど)を洗い流して、皮膚のバリア機能や健康を守るために行います。
ワンちゃんのシャンプーは、外からの汚れ(ゴミ・土・ホコリなど)と中からの汚れ(抜け毛・皮脂・フケなど)を洗い流して、皮膚のバリア機能や健康を守るために行います。
※ 皮膚トラブルのあるワンちゃんの場合、高い温度のお湯を使用すると皮膚のかゆみ・痛み・炎症の悪化につながってしまう場合があるので、30℃以下の温度が推奨される場合もあります。担当医の指示に従ってシャンプーを行うようにしましょう。
シャンプーをする前に、ブラシやコームを使って毛の流れを整えながら大きな汚れや抜け毛、古い角質(フケ)などを取り除きます。
ブラッシング・コーミングをしっかり行うことでシャンプーの時間を短縮することができ、ワンちゃんのストレス軽減にもつながります。
皮脂の分泌が多くて毛や皮膚がべたついていたり、汚れが多い場合は、シャンプーの前にクレンジングを行ったり、バスタブを使った入浴を行ったりします。
全身がべたついている場合は入浴用シャンプーや希釈タイプのクレンジング剤を使用して、シャンプー前の「下洗い」を行います。べたつきが部分的な場合はクレンジングオイルを使用します。皮膚や毛が濡れているとクレンジング剤の効果が落ちてしまうため、クレンジングはワンちゃんの体を濡らす前に行います。
※クレンジング剤は皮脂・脂汚れを落とすことに特化しているため、健康な皮膚を守るために必要な皮脂も落としてしまうことがあります。皮脂の不足は皮膚の乾燥や皮膚バリア機能の低下にもつながるため、クレンジングを行う際はシャンプー後に必ず保湿剤を使用するようにしてください。
シャンプー剤を使う前に、ワンちゃんの体全体をお湯で濡らします。
シャワーの水流で落とせる汚れをできるだけ落とすことで、シャンプーの効果がアップします。
※シャワーヘッドをワンちゃんの体に密着させて行うと、ワンちゃんが嫌がりにくいのでオススメです。
※顔周りにお湯がかかるのを嫌がってしまう場合は、スポンジにしみこませたお湯を絞ってやさしくかけてあげましょう。
シャンプー剤は、「ワンちゃんの体につける前にしっかりと泡立てておく」ことがとても重要です。事前にしっかりと泡立てておくことによって、皮膚への摩擦・刺激の軽減、効率よく皮脂を吸着してくれる、洗いムラやすすぎ残しの防止といったメリットがあります。
洗面器や桶にお湯とシャンプー剤を入れ、洗顔用の泡立てネットやスポンジを使って泡立てます。「手のひらをさかさにしても落ちない程度の、弾力あるきめ細かな泡」を目指しましょう。
※泡立てるのが難しい場合は、下記の方法もおすすめです。
・空のペットボトルにシャンプー剤と少量のお湯を入れて振る
・料理用ミキサーにシャンプー剤と少量のお湯を入れて混ぜる
・ゴシゴシ擦って泡立てることにより、毛や皮膚に摩擦刺激を与えてしまう
・シャンプー剤を塗った部位と他の部位で洗いムラが発生してしまう
・シャンプーの付けすぎ、使い過ぎにつながる
・シャンプーのすすぎ残しにつながる
十分に泡立てたシャンプーをワンちゃんの毛・皮膚に乗せ、毛の流れに沿ってなでるようにして塗り込んでいきます。
シャンプー剤の種類によっては、「シャンプーを塗ったあと数分間放置して、毛や皮膚になじませてから洗い流す」ように指示のあるものがあります。
ワンちゃんが数分間じっとしてくれない場合もあるので、「皮膚トラブルのある部位」「汚れが気になる部位」からシャンプーを塗り込むようにするのがおすすめです。
毛や皮膚にシャンプー剤が残らないように、シャワーを使ってしっかりと洗い流します。
ワンちゃんの毛から泡が出なくなって、軽くお湯をはじくようになったら、シャンプー剤が十分洗い流せている合図です。
シャンプーによって皮脂が洗い流されると皮膚が乾燥しやすくなってしまうので、皮膚を保護するために保湿剤を使用します。
お湯で薄めて体にかけるタイプ・スプレータイプなど様々なものがあるので、使いやすいものを選びましょう。
ワンちゃんの毛や皮膚を乾かすときは、「できるだけタオルドライで乾かす」ことを意識しましょう。毛を構成しているタンパク質は熱に弱く、ドライヤーの温風を長時間かけると、毛の潤いや柔軟性が失われてしまいます。また、皮膚に刺激を与えてトラブルの原因となる場合もあります。
「タオルドライで取りきれなかった水分をドライヤーで乾かす」イメージで行いましょう。
・吸水性の高いタオルを複数枚使い、ワンちゃんの全身をやさしく包むように当てて、毛に付いた水分をタオルに吸わせるようにして乾かします。
・タオルで拭きにくい部位は、キッチンペーパーやペットシーツなどを使うのもおすすめです。 ※ゴシゴシこするのはNG!
ドライヤーを使う際は、高温の風がワンちゃんの毛や皮膚に直接当たらないように、オーナー様の手で温度を確認しながら乾かしましょう。
温風と冷風を交互に使うと、毛や皮膚が熱くなりにくいのでおすすめです。
夏は扇風機、冬は暖房器具を使って、部屋の湿度を下げておくとドライヤー時間の短縮につながります。
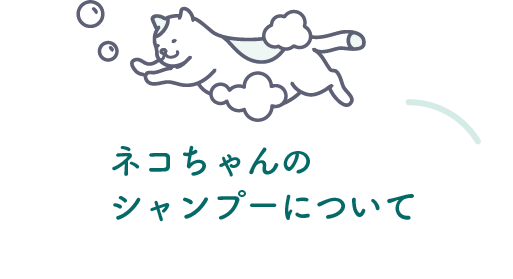 ネコちゃんはとてもきれい好きな動物で、口や手足を器用に使った「グルーミング」によって全身をきれいに保っています。多い時には1日の15%をグルーミングに費やしているともいわれており、一般的に「十分なグルーミングができていれば、ワンちゃんのような定期的なシャンプーは不要」だといわれています。
ネコちゃんはとてもきれい好きな動物で、口や手足を器用に使った「グルーミング」によって全身をきれいに保っています。多い時には1日の15%をグルーミングに費やしているともいわれており、一般的に「十分なグルーミングができていれば、ワンちゃんのような定期的なシャンプーは不要」だといわれています。
しかし、ネコちゃんの中にはグルーミングが不得意で、オーナー様がブラッシングやシャンプーでケアをしてあげる必要のある子がいます。また、皮膚トラブルの治療の一環としてシャンプーが必要になったり、体が汚れてしまってシャンプーが必要になる場合もあります。
多くのネコちゃんが体が濡れることやシャワーの音を嫌がってしまうため、日頃のケア・スキンシップの延長として少しずつシャンプーに慣れさせてあげることをおすすめします。
ネコちゃんの場合もシャンプーの方法は基本的にワンちゃんと同様なのですが、以下の点を特に注意してください。
シャンプーの時間をできるだけ短くすることが、ネコちゃんのストレス軽減につながります。シャンプー前のブラッシングや日常ケアによってできるだけ汚れを落としておきましょう。
広い浴室や浴槽の中で直接シャンプーをしようとするとネコちゃんが落ち着かない場合があるので、ネコちゃんの体のサイズに合わせたペット用バスタブを使用しましょう。
シャワーの音を嫌がるネコちゃんが多いので、「シャワーヘッドを取り外して使用する」「シャワーヘッドにタオルを巻いて音を軽減する」「シャワーを使用せず洗面器・桶からお湯をかける」などの工夫をしてあげましょう。
皮膚トラブルなどでネコちゃんのシャンプーが必要になった場合も、ネコちゃんが嫌がる場合は無理に全身を洗おうとせず、特に症状がひどい場所を中心にできる範囲で実施しましょう。ご自宅でのケアが難しい場合は、動物病院やペットサロンに相談してみてください。
